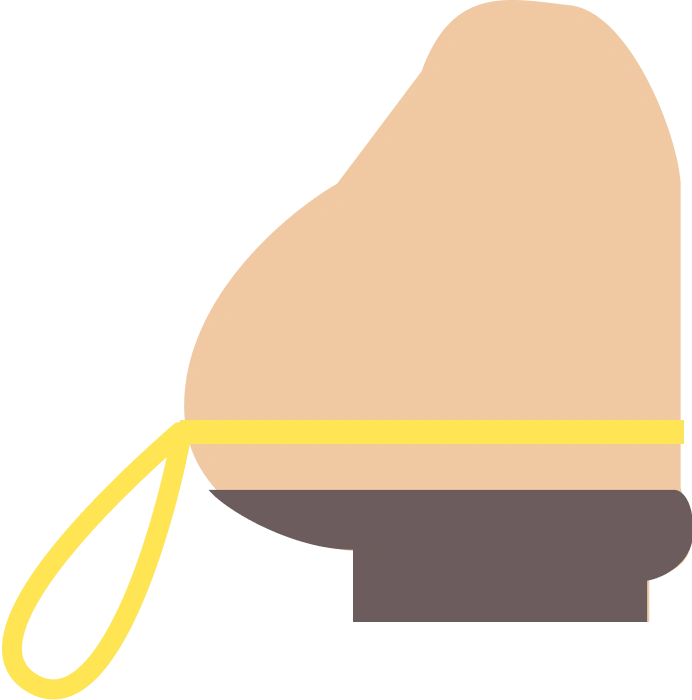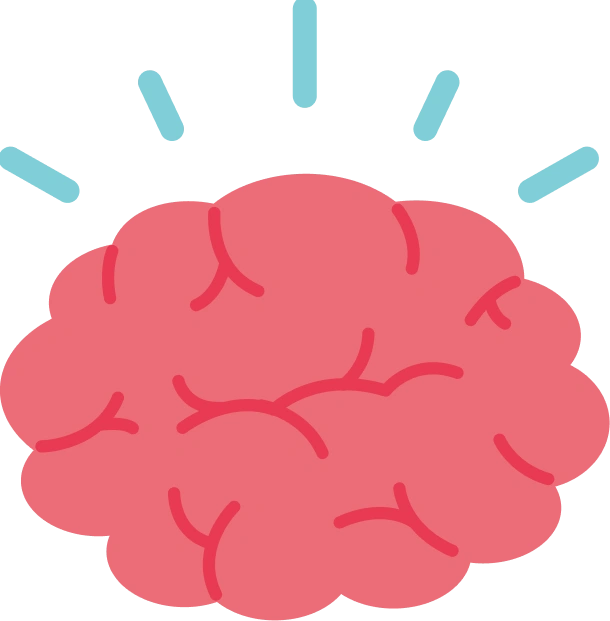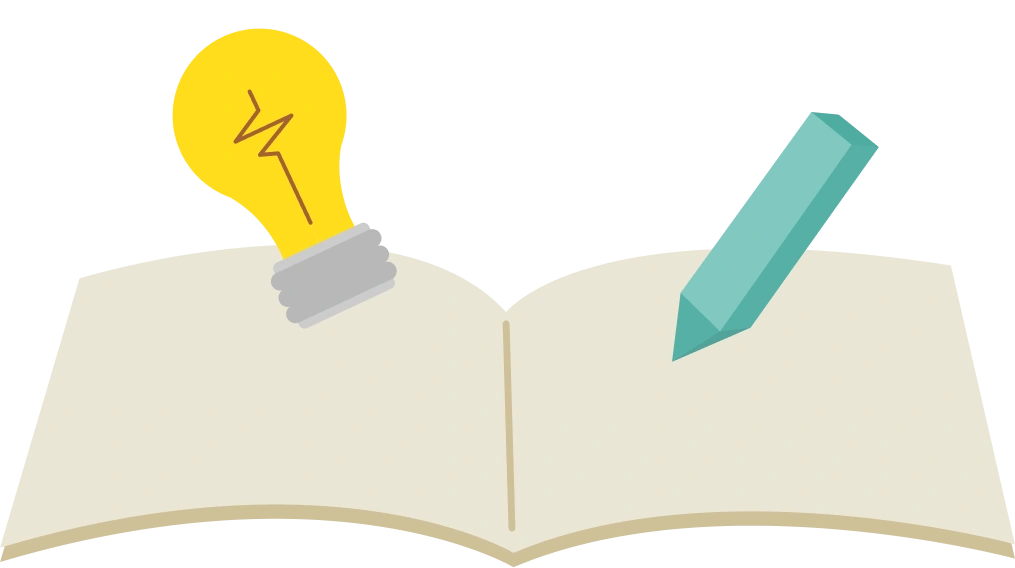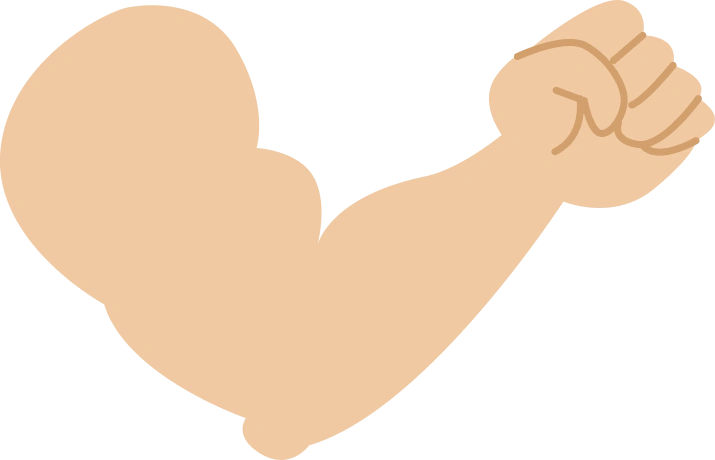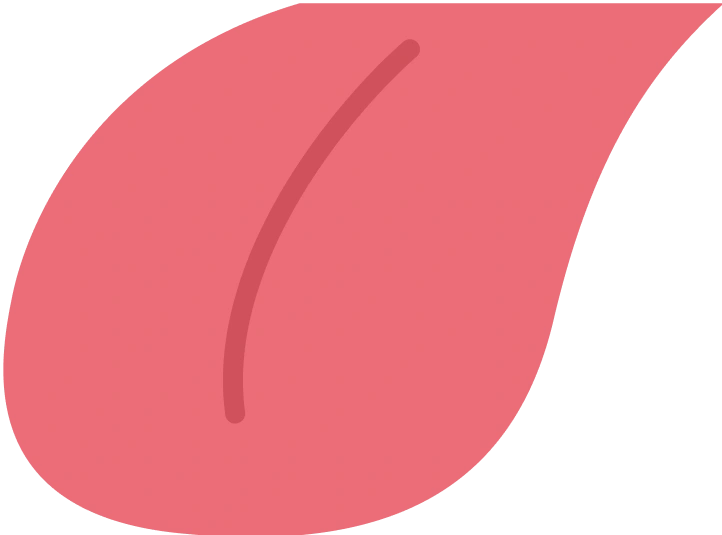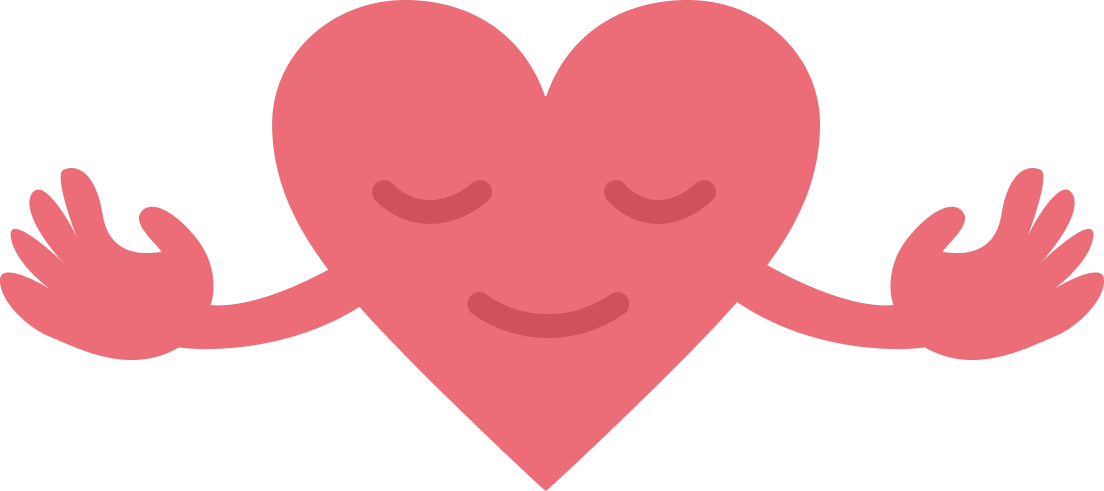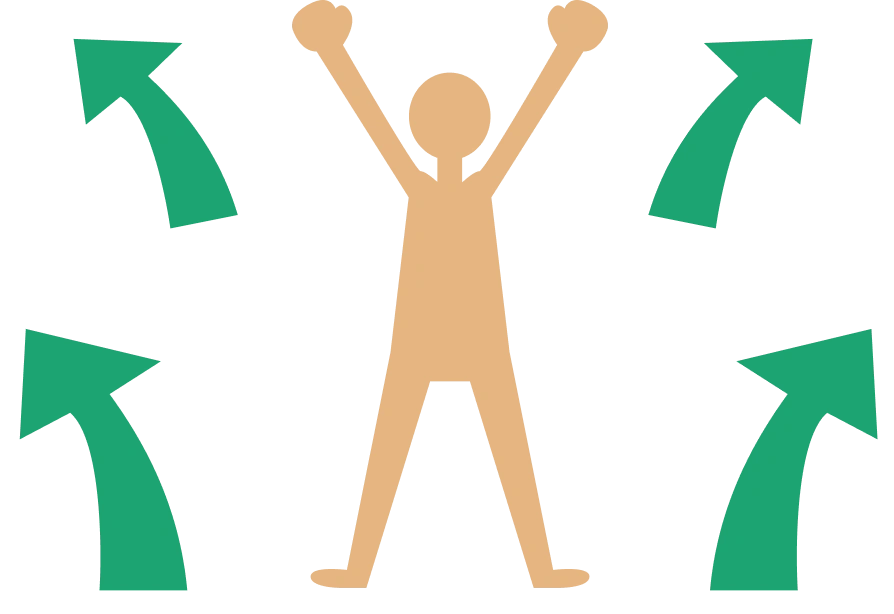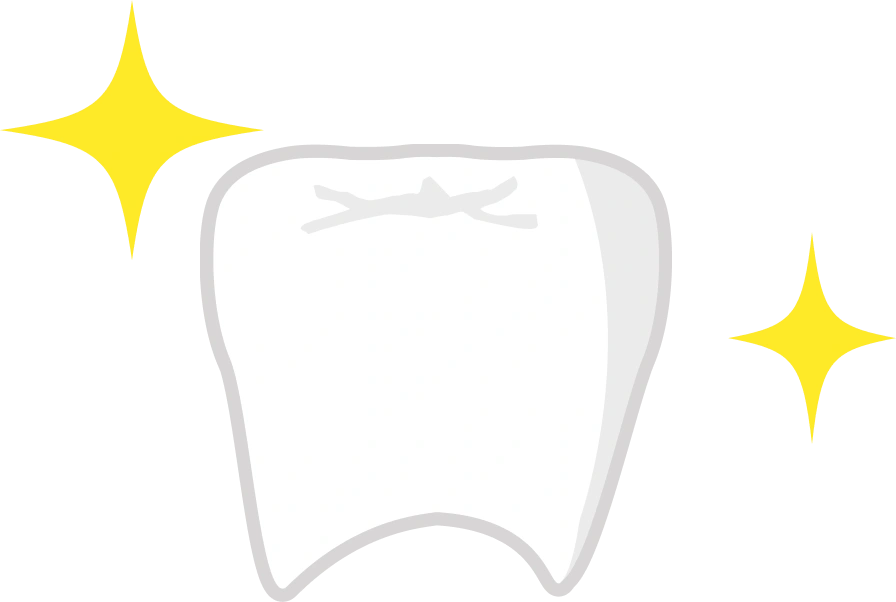噛むことの効果
「よく噛んで食べましょう」——その言葉には、驚くほどたくさんの“いいこと”が詰まっています。
噛むことで、消化が助けられ、脳が活性化し、心も落ち着く。
子どもから高齢者まで、すべての世代にうれしい効果がある咀嚼の力。
このページでは、噛むことがもたらすさまざまなメリットを、わかりやすく紹介します。
噛むことで、消化が助けられ、脳が活性化し、心も落ち着く。
子どもから高齢者まで、すべての世代にうれしい効果がある咀嚼の力。
このページでは、噛むことがもたらすさまざまなメリットを、わかりやすく紹介します。
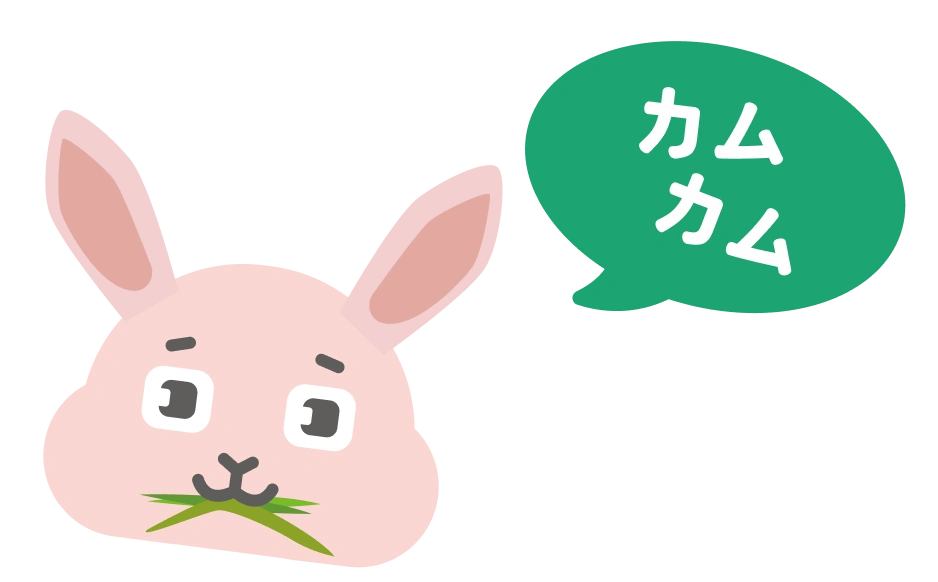

噛むことの効果
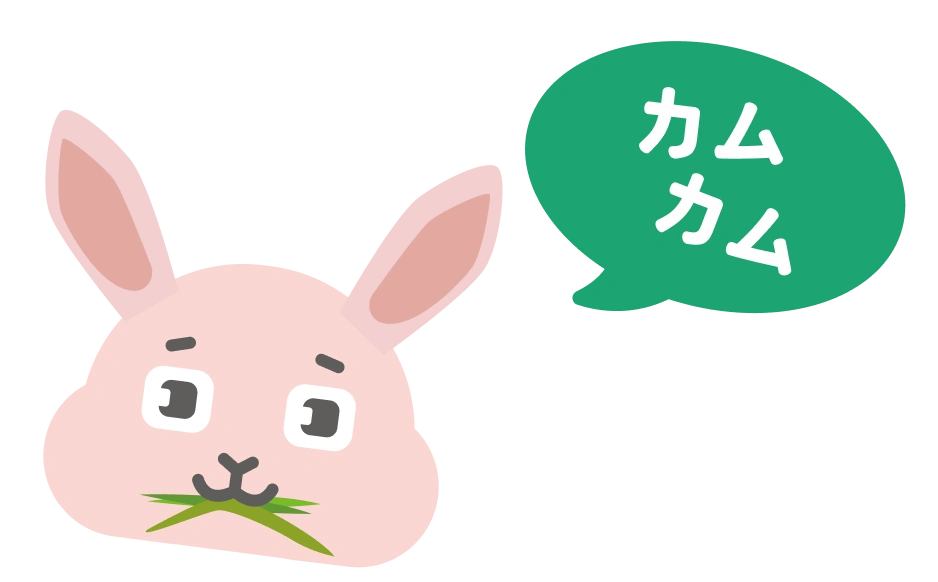
「よく噛んで食べましょう」——その言葉には、
驚くほどたくさんの“いいこと”が詰まっています。
噛むことで、消化が助けられ、脳が活性化し、
心も落ち着く。
子どもから高齢者まで、
すべての世代にうれしい効果がある咀嚼の力。
このページでは、
噛むことがもたらすさまざまなメリットを、
わかりやすく紹介します。
驚くほどたくさんの“いいこと”が詰まっています。
噛むことで、消化が助けられ、脳が活性化し、
心も落ち着く。
子どもから高齢者まで、
すべての世代にうれしい効果がある咀嚼の力。
このページでは、
噛むことがもたらすさまざまなメリットを、
わかりやすく紹介します。